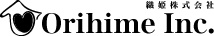【投資家向け】エシカル消費の拡大と企業による対応策を解説
 エシカル消費とは、環境や社会に配慮した倫理的な消費行動のことです。
エシカル消費とは、環境や社会に配慮した倫理的な消費行動のことです。近年、深刻化する地球環境問題や社会的格差を背景に、SDGsへの関心とともに注目を集めています。
環境意識の高い若い世代を中心に、「買い物を通じて社会に貢献する」という考え方が着実に広がりを見せています。
エシカル商品は従来製品と比べて価格が割高となる傾向があり、また実店舗での品揃えも限られているのが現状です。
本記事では、投資家の視点から、エシカル消費市場の拡大が企業にもたらすビジネスチャンスと課題、そして企業価値向上への影響について詳しく解説していきます。
エシカル消費とは?

なぜ今「エシカル消費」が注目されているの?
「エシカル」な消費が重要視される背景には、主に2つの社会課題があります。1つは、地球温暖化や海洋汚染、生態系の破壊といった環境問題への危機感の高まりです。
2つ目は、途上国での児童労働や低賃金労働など、グローバルな社会的不平等への意識の向上になります。
これらの課題に対して、消費者が購入する商品やサービスを通じて解決に寄与できる考えが広まっています。
エシカル消費とSDGsの関係
2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」とも深く関連しており、ゴール12「つくる責任 つかう責任」は、持続可能な生産・消費形態を確保することを目指しています。日本国内では消費者庁が中心となってエシカル消費の普及・啓発活動を展開しており、多くの自治体や企業も独自の取り組みを始めています。
身近にあるエシカル消費はどんなものがあるの?

リサイクル品や形が少し曲がった野菜を選ぶ
規格外野菜とは、形や大きさが市場の基準に合わないために流通から外される野菜のことです。曲がったキュウリや大きすぎるジャガイモなど、これらの野菜は見た目が基準と異なるだけで、栄養価や味わいは通常の野菜と変わりません。
しかし残念なことに、見た目だけで価値が低く見られ、多くが廃棄されているのが現状です。
農林水産省のデータによると、日本では年間約612万トンもの食品ロスが発生しており、その一部は規格外野菜によるものです。
このような状況を改善するため、私たち消費者にもできることがあります。
例えば、スーパーマーケットやファーマーズマーケットで規格外野菜を見かけたら、積極的に購入してみましょう。
形は少し歪んでいても、同じように美味しく調理できます。
また、衣類や家具などのリサイクル品を選ぶことも、環境への大切な一歩となります。
動物にやさしい方法で作られた商品を選ぶ
動物福祉(アニマルウェルフェア)への配慮は、倫理的な消費行動の重要な一環として、動物だけでなく環境や社会全体にも良い影響をもたらします。例えば、ストレスの少ない飼育環境で育った家畜は、質の高い食品を提供するだけでなく、生産者の幸福や尊厳にもつながりやすいです。
また、消費者がこうした商品を選ぶことで、持続可能な生産方法への需要が高まり、社会全体での意識向上が期待されます。
エシカル消費を企業が取り組むメリットは?
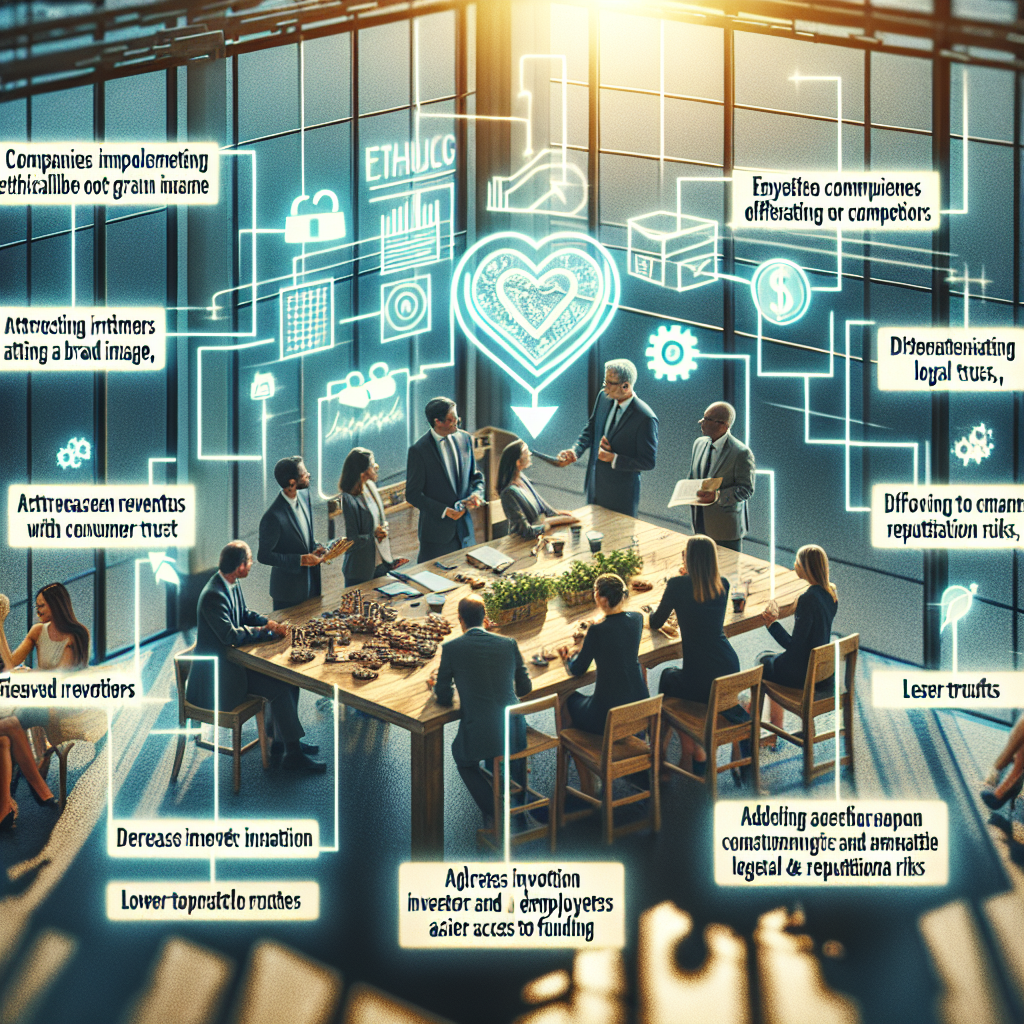
「良い会社」というイメージアップが期待できる
エシカル消費(環境や社会に配慮した消費行動)に基づいて事業活動を行う企業は、持続可能な社会の実現に貢献する企業として高く評価されています。このような取り組みは、企業の社会的責任(CSR)やSDGsへの積極的な姿勢として認識され、強固なブランドイメージの構築につながるでしょう。
また、消費者からも好意的に受け止められやすいです。
消費者庁の調査によれば、エシカル商品やサービスの提供が企業イメージ向上につながると考える人は79.6%に達しています。
「買ってみたい」と思う新しいお客様の獲得
現代の消費者は、単なる価格や品質だけでなく、環境への配慮や人権尊重といった社会的価値にも重きを置くようになっています。近年は、エシカル消費への関心が若い世代を中心に着実に高まっています。
消費行動の変化を踏まえ、社会・環境に配慮した商品やサービスを提供する企業は、競合他社との明確な差別化を図り、持続可能な成長基盤を構築しやすいです。
ESG投資家からの信頼を高める
ESG投資家は、持続可能な社会の実現に向けた企業を重視し、高く評価します。フェアトレード商品の取り扱いや再生可能エネルギーの活用など、エシカル商品やサービスを提供する企業は、消費者からの支持に加え、投資家からも高い評価を得る傾向にあります。
エシカル消費の拡大による企業の対応策とは?

商品の作り方や仕入れ方を見える化する
Z世代やミレニアル世代では、サプライチェーン全体の透明性や倫理的な取り組みを重視する傾向が強まっています。このため、企業が積極的に情報を開示することでブランド価値を向上させ、消費者との信頼関係が強化しやすいです。
このような消費者ニーズに応えるため、企業は具体的な取り組みを進めています。
例えば、生産工程でフェアトレードの原材料を使用していることや、労働環境に配慮していることを明確にすることで、消費者からの支持を得やすいです。
さらに、認証マーク(例:フェアトレード認証、有機JASマーク)を取得することで、消費者が環境や社会に配慮した商品(エシカルな商品)を簡単に識別できる仕組みも有効です。
環境に優しい商品やサービスを増やす
気候変動や資源枯渇といった地球規模の環境問題が深刻さを増す中、企業には環境負荷を軽減する商品やサービスが求められています。
具体例として、リサイクル素材を活用した製品や再利用可能なアイテムの提供は、資源の効率的利用と廃棄物削減に直接的に寄与しやすいです。
また、環境意識の高い消費者からの支持獲得にもつながり、企業イメージの向上にも効果的です。
環境保護や社会貢献を強化している「資生堂」の成長性は?
 資生堂は、環境保全への強い使命感から、「資生堂5Rs」という独自の環境方針を掲げています。
資生堂は、環境保全への強い使命感から、「資生堂5Rs」という独自の環境方針を掲げています。この革新的な方針は、以下5つのRを軸に展開され、限りある資源の最適活用を目指しています。
- リスペクト(尊重)
- リデュース(削減)
- リユース(再使用)
- リサイクル(再生利用)
- リプレース(代替)
これにより、製品のライフサイクル全体で環境負荷を効果的に軽減することが可能です。
具体的な取り組みとして、資生堂はプラスチック使用量の削減に注力しています。
例えば、詰め替え可能な「リフィル型容器」の拡充や、環境負荷の少ない再生可能素材を活用した革新的なパッケージの開発を積極的に推進しています。
このような取り組みは、消費者に環境に配慮した選択肢を提供するとともに、企業としての独自の価値創造にもつながっているのです。
環境配慮型の取り組みは、エシカル消費への関心が高まる現代社会において、多くの消費者から強い支持を得ています。
実際、資生堂の環境配慮型製品の売上は年々増加傾向にあり、ブランド価値の向上にも貢献しています。
まとめ
今回はエシカル消費に関する基本的な仕組みから企業による対応策まで解説しました。企業にとって、エシカル消費への対応は単なる社会貢献の枠を超えています。
ブランド価値の向上やESG投資家からの信頼獲得につながる重要な経営戦略として位置づけられ、具体的な取り組みも多様化しています。
特に若い世代を中心にエシカル消費への関心は着実に高まっており、今後は企業の競争力を左右する重要な要因となることが予想されます。
このような時代の流れを見据え、企業としてどのように対応すべきか、さらに深く知りたい方は、ぜひ無料で学べる「北川流投資術」の講座をご覧ください。
詳細はこちらから▶ 無料動画講座を視聴する